
環境を変えることは 自分を変える大きなチャンス
黒住 龍彦さん(岡山県)
令和6年度卒業生 / 文系×陶芸デザインコース
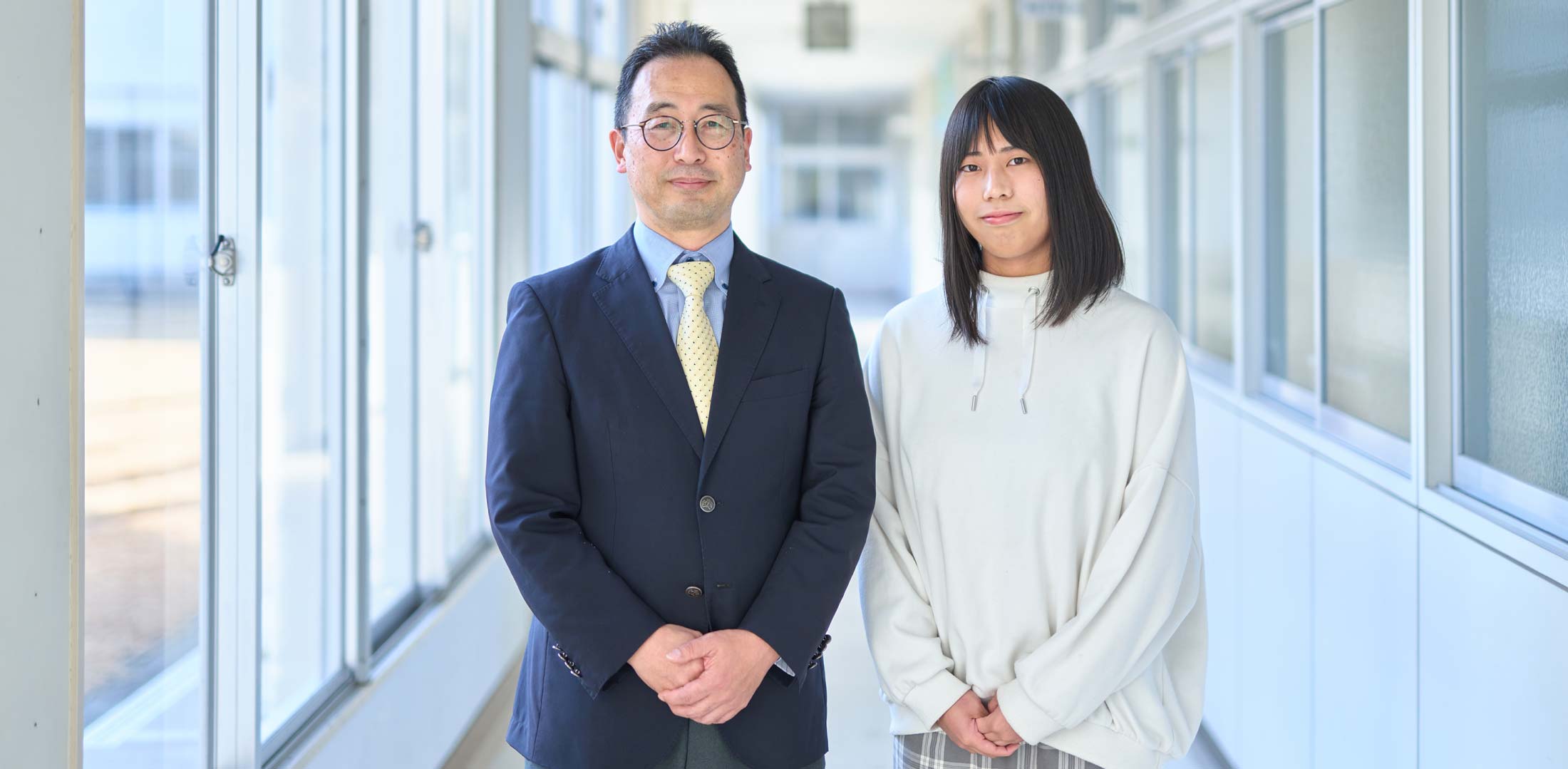
令和6年度卒業生 佐藤つぐみさんの保護者 / 三児の父

子どもが中学1年生の時に起立性調節障害を発症し、朝起きられず、時間通りに登校できなくなりました。通っていた中高一貫校の内部進学をやめ、他校への進学を検討することに。
当初は妻が勧める通信制高校も選択肢にありました。吉備高原学園高校を知り、オープンスクールに参加してみると、この静かな環境が、感覚過敏の傾向がある彼女にとって心地よく感じられたようです。また、全寮制なら親にも甘えずに頑張れるからと「自立するために寮に入ってみたい」と言う本人の気持ちを尊重し、全寮制への進学を決めました。
入学後しばらくは朝起きるのはかなり辛かったのではないかと思います。それでも自分で決めて、友達と励まし合って頑張っている様子を聞いて、とても誇らしく感じていました。
うちは子どもが3人いるのですが、長女は進学で既に県外に出ており、次女である彼女が寮に入ったことで、長男と妻との3人暮らしに。子どものために使っていた時間が減ったことで、これまでの家族との生活すべてが大切な思い出であったことに気づきました。離れて暮らしていても、家族が生きて元気でいてくれることに感謝があふれてくるようになりました。


進路を選ぶ上で大切なのは、本人が自分の人生を主体的に考えられること。そのために、できるだけ多くの選択肢を用意してあげるのも、親の大切な役割だと考えています。
現在、高校の選択肢は「全日制」「通信制」「全寮制」と多様で、子どものタイプによってそれぞれにメリット・デメリットがあると思います。例えば、中学校時代に不登校だった場合、通信制を選ぶことが多いと感じます。それが諦めではなく、本人が自ら「行ってみたい」と思えるなら良い選択だと思います。
一方で、吉備高原学園高校では、他の学校にはない貴重な経験が得られます。子どもたちの個性を磨ける専門コースがあったり、静かな環境で自分自身を見つめ直せたり、友人たちとの濃い関わりがあったり。特に、寮生活を通じて、人間関係はもちろん、生活全般、社会で生きていくためのたくさんの学びがあったように感じています。
全寮制が合う合わないもチャレンジして初めてわかります。どんな学校でも、最初は不安です。でも、迷うぐらいならGO! 実際、通信制からここに来た子もいれば、逆にここから通信制に移った子もいます。他の全日制から編入してくる子もいます。まずはオープンスクールで、学校の雰囲気を肌で感じ、自分にとってプラスになると少しでも感じたら、ぜひチャレンジしてみてほしいと思います。

うちの子のような起立性調節障害で、体調が悪く症状が重いような場合は、進学を焦るよりも、まずは治療を優先した方がいいと思います。でも、それなりに回復して、本人に「行ってみたい」と思う気持ちがあるなら、大丈夫です。きっと朝になったら、起きるようになりますから。でも、起きられない日もたまにはあります。それでもいいと思うんです。頑張ってみようと思ったことが大事ですから。
そこでもし、先生が「そんなんじゃダメだろー」と、スパルタみたいなことをやっていたら、子どもはプレッシャーを感じて、苦しくなっていたと思います。吉備高原学園高校の先生方は、子どもたち一人ひとりの体調やペースに寄り添いながら関わってくださるので、信頼しています。
起床時間になると点呼が行われるのですが、時々、「誰々さんは部屋にいまーす」と友人が答える。先生がそのあと声をかけには行くのですが、そういうことも一応許されているみたいです。もちろんずっとはダメですけど。規則だけじゃない、人として尊重してくれる、そんなあたたかみのある学校です。
若い時に家族以外の人と深く関わった経験は、必ず人生に活かされます。先生だけでなく、同級生や先輩、後輩と共に過ごす日々の中で、楽しいこともあれば、時にはぶつかることもある。すべて大切な経験です。お互いに全く違う環境で育った者同士が、相手を理解しようと努力し、折り合いのつけ方、適切な距離感を肌で学んでいく。これからの人生で、ここまでの濃い人間関係を学ぶ機会は、もうないかもしれませんよね。
また、家族と暮らさないことで、それまで当たり前に感じていたことが、どれだけありがたいものだったのかを初めて知り、感謝の気持ちが自然と芽生えてきます。10代後半で、こうしたことに気づけるチャンスがあることは、お金に変え難い経験だと思っています。
「大変だ」と思えば大変に感じますが、「貴重な経験だ」と思えば、宝物になります。すべては捉え方次第。行動することで見えてくることがたくさんあります。楽しく、一歩前へ進んでみてほしいと思っています。


離れて暮らすことで、親との関係性にも変化がありました。以前は些細なことでぶつかることもありましたが、月に一度の帰省がちょうど良い距離感となり、お互い落ち着いて対等に話せるようになりました。また、入学を決めた時に背中を押してくれたこと、そして入学後もずっと支え続けてくれたことに、とても感謝しています。
インタビューを読む