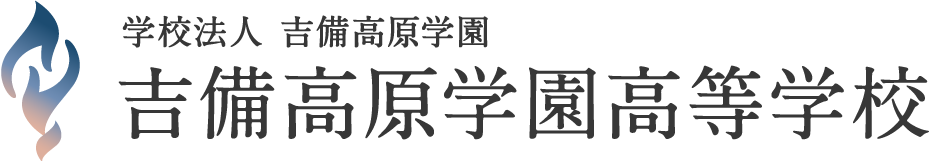- すべて
- 不登校
学校に行きたくない理由と親ができるサポート|NG行動と解決策
- 子どもが「学校に行きたくない」本当の理由
- 学校に行きたくないと思うのは自然なこと
- 学業や部活のプレッシャー
- 人間関係の悩み(友達や恋愛)
- 親からのプレッシャー
- 子どもの年齢別「学校に行きたくない」と言われたときの対処法
- 小学生の場合
- 中学生の場合
- 高校生の場合
- 親ができるサポート方法
- 常に味方でいるという姿勢
- 聞き手に徹する
- 子どもの気持ちに寄り添うコミュニケーション
- 親が避けるべきNG行動や言動
- 無理に学校に行かせようとする
- 親の価値観や期待を押し付ける
- 子どもの問題に過度に干渉する
- 否定的な言葉遣いをする
- それでも不登校になってしまったら?進学先の選択肢として考えられる学校
- 定時制高校や通信制高校という選択肢
- 親元を離れて全寮制の学校に通う選択肢
- 高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)という選択肢
- まとめ
- 吉備高原学園高等学校の全寮制
「学校に行きたくない…」ある日突然、お子さんからそう告げられたとき、多くの保護者様は深い不安と戸惑いに包まれることでしょう。もし今、あなたのお子さんが学校へ行くことに困難を抱えているとしたら、それは決してあなたやご家庭だけの特別な悩みではありません。まずはじめに知っていただきたいのは、その経験は今や、日本全体が向き合うべき共通の課題となっているという事実です。
文部科学省が令和6年10月に発表した最新の調査によれば、令和5年度における小・中学校の不登校児童生徒数は、過去最多の346,482人(在籍者の3.7%)に達しました。高等学校においてもその数は68,770人(在籍者の2.4%)にのぼり、これもまた過去最多を記録しています。その中でも特に顕著なのは中学生で、約15人に1人が不登校の状態にあり、これは多くの子どもたちが学校生活において何らかの困難を抱えていることの表れです※1。
※1 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
| 学校種別 | 不登校児童生徒数 | 在籍者に占める割合 |
| 小学校 | 130,370人 | 2.1% (約47人に1人) |
| 中学校 | 216,112人 | 6.7% (約15人に1人) |
| 高等学校 | 68,770人 | 2.4% (約41人に1人) |
(出典:文部科学省「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」)
お子さんが「学校に行きたくない」と感じる背景には、一人ひとり異なる、そしてしばしば複雑な理由が隠されています。親としては、その苦しみを理解し、適切にサポートしたいと願うのは当然のことです。
本記事では、子どもたちが抱える「学校に行きたくない」理由をデータと共に探り、親としてできる具体的なサポート方法、そして良かれと思ってついやってしまいがちな「NG行動」について、専門的な視点も交えながら詳しく解説します。お子さんの心に寄り添い、共に未来を考えるための一助となれば幸いです。
子どもが「学校に行きたくない」本当の理由
子どもが学校を休むとき、その背景には単純な「怠惰」ではない、様々な心の葛藤が存在します。まずは、子どもたちがどのような理由で学校から足が遠のいてしまうのか、その一端を理解することから始めましょう。
学校に行きたくないと思うのは自然なこと
「学校に行きたくない」という気持ちは、子どもにとって決して珍しいものではありません。大人でも仕事に疲れて休暇を取りたくなるように、子どもたちが学校生活にプレッシャーや疲れを感じ、「休みたい」と思うのはごく自然な感情です。大人だって有給休暇を使って休むことがあるように、子どもたちも、毎日の授業や部活動、そして友人関係などで、心身に大きな負担をかかっていることがあります。
学業や部活のプレッシャー
多くの中学生や高校生は、学業や部活の成績に対するプレッシャーを感じています。文部科学省の調査でも、不登校の要因として「学業の不振」が中学生で15.5%、高校生で15.4%を占めています。※2 テストの点数でクラスメイトと比較されたり、部活動のレギュラー争いで思うような結果が出せなかったりすることで、自信を失い、学校に行く気力をなくしてしまうのです。
※2 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
人間関係の悩み(友達や恋愛)
思春期に入ると、友人関係はより複雑になります。文科省の調査では、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」が不登校の要因として中学生で14.4%、高校生で11.0%と※3 報告されています。仲間外れにされることへの恐怖、グループ内での窮屈さ、あるいは特定の友人との些細なすれ違いが、学校全体を「居心地の悪い場所」に変えてしまうことがあります。
また、恋愛に関する悩みも、この時期の子どもたちの心を大きく揺さぶります。相手の気持ちが分からなかったり、友人関係との板挟みになったりすることで、感情が大きく浮き沈みして、学校生活そのものに集中できなくなるケースも少なくありません。
※3 令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について
親からのプレッシャー
そして、見過ごされがちですが、その背景に親との関係が影響しているケースも少なくありません。例えば、親心からの「勉強しなさい」「部活も頑張りなさい」といった期待が、知らず知らずのうちに子どもを追い詰め、学校を苦痛な場所にしてしまうことがあります。
テストの結果が悪かったときに厳しい言葉をかけられたり、期待に応えられなかったことで自分を責めてしまったりする子どももいます。また、子どもの意見を聞かずに親が進路を決めてしまうなど、親の価値観の押し付けが、学校への意欲を失わせてしまうこともあるのです。
子どもの年齢別「学校に行きたくない」と言われたときの対処法
「学校に行きたくない」という言葉の背景にある理由は、子どもの発達段階によっても異なります。ここでは、年齢別の主な原因と、親として心掛けたい対処法について解説します。
小学生の場合
小学生の不登校の主なきっかけとしては、「無気力・不安」に次いで「親子の関わり方」や「生活リズムの乱れ」が挙げられます。友達との些細なトラブルや、授業についていけないといった学習面のつまずきも、学校への不安感を増大させます。また、家庭環境の変化(転居、家族構成の変化など)に敏感に反応することもあります。
小学生はまだ自分の気持ちをうまく言葉にできないことが多いため、安心して話せる環境づくりが何よりも大切です。子どもの表情や仕草にも注意を払いながら、少しずつ本音を引き出すように心がけましょう。学校での出来事を具体的に尋ねるよりも、「好きな遊びの話」や「楽しかったこと」など、ポジティブな会話からコミュニケーションの糸口を見つけるのも良いでしょう。
中学生の場合
中学生になると、友人関係がより複雑になり、学業や部活動でのプレッシャーも増大します。文科省の調査でも、不登校のきっかけとして「無気力・不安」が5割を超え、「学業の不振」や「いじめを除く友人関係の問題」が顕著になります。
この年代では、思春期に入り、恋愛や友達関係の悩みも加わり、心の葛藤が学校への意欲に影響を与えることがよくあります。自己主張が強くなる一方で、他者との比較に敏感になりやすく、劣等感やコンプレックスを抱きやすくなるのもこの時期の特徴です。
親としては、子どもの話を否定せずに聞き、良き相談相手になることが求められます。「今日はどんなことがあったの?」といった日常の会話を大切にし、子どもがいつでも本音を話せる信頼関係を築くことが第一歩です。
高校生の場合
高校生になると、大学進学や就職といった将来の進路を考え始める年齢であり、進学や就職といった進路に対するプレッシャーや、部活、友人との関係、親の期待に答えなければならないという思いが重荷になることがあります。実際の統計でも「進路に係る不安」が不登校の要因として4.1%を占め、これは小中学校と比較して高い割合を占めます。
具体的な悩みではなくとも、進学先に関する不安や自分の将来に対する漠然とした恐れも「学校に行きたくない」という気持ちに繋がる場合があります。また、恋愛や友人関係についても、気持ちの変化が大きなストレスとなり、学校に行く意欲を削ぐことがあります。
この時期の子どもには、一方的なアドバイスではなく、一人の人間として対等に向き合い、一緒に将来を考えるパートナーとしての姿勢が大切です。「どんなことに興味がある?」「どんな大人になりたい?」といった問いかけを通じて、子ども自身が自分の人生を考える手助けをしてあげましょう。
親ができるサポート方法
常に味方でいるという姿勢
親としてできる最も大切なサポートは、「子どもが安心して話せる環境を作ること」です。お子さんが悩みを打ち明けやすいように、「あなたの味方だよ」というメッセージを伝え続け、普段からコミュニケーションを取れるような関係性を築くことが大切です。
聞き手に徹する
お子さんが話し始めたときは、アドバイスや意見を言いたくなる気持ちをぐっとこらえ、まずは「聞き手に徹する」ことが何よりも大切です。お子さんの言葉を遮らず、相槌を打ちながら、ただひたすら耳を傾ける。それだけで、お子さんの心は軽くなり、「分かってもらえた」という安心感を得ることができます。
「そうだったんだね」「つらかったね」と、気持ちに共感する言葉を伝えましょう。そして、もしお子さんから相談されたときには、答えを出してあげるのではなく、様々な情報を提供し、お子さん自身が常に選択肢を持ち、自ら答えを出せるようにサポートしてあげることが、親としての重要な役割です。
子どもの気持ちに寄り添うコミュニケーション
「学校に行きたくない」という言葉の裏には、お子さん自身も言葉にできない複雑な感情が渦巻いていることが少なくありません。親としては心配のあまり、「なんで?」「どうして?」と理由を問い詰めたくなりますが、それは避けましょう。
大切なのは、お子さんの気持ちを否定せず、丸ごと受け止めることです。「学校で何かあったの?」と優しく尋ね、「「今はゆっくり休んでいいんだよ」と安心感を与える言葉をかけてあげましょう。お子さんが安心して本音を話せる温かいコミュニケーションを心がけましょう。
親が避けるべきNG行動や言動
お子さんを想うあまり、良かれと思って取った行動が、逆にお子さんを追い詰めてしまうことがあります。ここでは、代表的なNG行動をいくつかご紹介します。
NG①:無理に学校に行かせようとする
子どもが「学校に行きたくない」と言っているときに、無理に行かせようとするのは逆効果です。「学校に行きたくない」というお子さんの訴えは、心身からのSOSサインです。その理由を十分に理解しないまま無理やり登校させようとすると、お子さんは「自分の気持ちを分かってもらえない」と感じ、親への不信感を募らせてしまいます。まずは「行けない」という現状を受け入れ、なぜ行きたくないのかを一緒に考える姿勢が大切です。
問題解決を急ぐのではなく、自分で答えを出せるようになるまで、お子さんの心と体を休ませることを優先しましょう。そして、お子さんの興味や得意なことを尊重し、一緒に楽しめる活動を見つけることも大切です。ゲームや読書、スポーツなど、お子さんが夢中になれるものがあれば、一緒に時間を過ごし、失われた笑顔や自信を取り戻すきっかけを作ってあげてください。
NG②:親の価値観や期待を押し付ける
「普通は学校に行くものだ」「良い大学に入ってほしい」といった親の価値観や期待を無理に押し付けることもNG行動の一つです。親の期待に応えられない自分を責め、自己肯定感を低下させてしまう原因にもなりかねません。大切なのは、世間一般の「普通」ではなく、お子さん自身の気持ちとペースを最優先に考えることです。そして大切なのは「子どもの人生の主役はお子さん自身である」ということです。親の役割はお子さん自身が自分で自分の生き方を選択できるようサポートするところまでです。
NG③:子どもの問題に過度に干渉する
お子さんの問題を解決しようと、すぐに学校に連絡したり、友人に事情を聞いたりするなど、親が先回りして行動してしまうことがあります。しかし、こうした過干渉は、お子さん自身が問題と向き合い、解決する力を育む機会を奪ってしまいます。
また、子どもが学校に行きたくない理由を「いじめが原因に違いない」「勉強が嫌なんだろう」と、親が原因を決めつけてしまうのもNGです。お子さんの話をじっくりと聞き、本人がどう感じ、どうしたいのかを尊重することが、自立へのサポートに繋がります。
NG④:否定的な言葉遣いをする
子どもが悩みを打ち明けたときに、「それは間違っている」「あなたが悪い」といったように、子どもの主張を真っ向から否定すると心を閉ざしてしまう原因になります。「親にはわかってもらえない」と感じた子どもは、次第に本音を話さなくなり、一人で抱え込んだり、反発するようになるなど、孤立を深めてしまうこともあります。
また、一見やさしさからの言葉であっても、「そんなことないよ」や「頑張りなさい」といった言葉も注意が必要です。これらの言葉は、子どもの気持ちを軽く扱われたと受け取られ、逆に傷つけてしまうことがあります。まずは子どもの感じたことを「そうだったんだね」と受け止め、共感を示すことが何よりも大切です。
それでも不登校になってしまったら?進学先の選択肢として考えられる学校
定時制高校や通信制高校という選択肢
定時制高校や通信制高校は、毎日決まった時間に登校する全日制とは異なり、柔軟な学習スタイルを提供しており、心身の負担が少なく、不登校を経験した多くの生徒が新たなスタートを切っています。特に通信制高校は、自分のペースで学習を進められる自宅学習が中心のため、対人関係に不安を抱えるお子さんにとっても選択しやすい環境です。
親元を離れて全寮制の学校に通う選択肢
もしお子さんに「今の環境をリセットしたい」「親元を離れて自立したい」という気持ちがあるなら、全寮制の学校も有力な選択肢です。規則正しい共同生活を通じて生活リズムを整え、同じような経験を持つ仲間と支え合いながら、深い人間関係を築くことができます。学習面だけでなく、生活全般のサポートが受けられるため、安心して学業に集中できる環境が整っています。
高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)という選択肢
万が一、高校を中退してしまったとしても、道は閉ざされません。「高卒認定試験」に合格すれば、高校卒業者と同等以上の学力があると認められ、大学や専門学校の受験資格を得ることができます。高校の在籍にこだわらず、自分のペースで学習を進め、次のステップを目指すためのセーフティネットです。どうしても高校生活に馴染めない場合でも、悲観しすぎずに前向きに考え、子どもにとって最適な道を一緒に考えてサポートすることが大切です。親として何があっても味方であることを子どもに伝え、励ますことが大きな支えになります。
まとめ
お子さんが「学校に行きたくない」と口にするとき、その心はSOSを発しています。親としてできる最も大切なことは、まずそのサインを受け止め、お子さんが安心して羽を休められる「安全基地」になることです。
理由を問い詰めたり、無理に登校させたりするのではなく、まずはお子さんの気持ちにじっくりと耳を傾け、共感する姿勢を見せましょう。
不登校になったことは問題視するべき出来事なのではなく、お子さんが自分に合った生き方や学び方を見つけるための、大切な「転機」なのかもしれません。お子さんのペースを尊重し、様々な選択肢があることを伝えながら、明るい未来へと一緒に歩んでいきましょう。
吉備高原学園高等学校の全寮制
不登校のお子さんが抱える様々な課題に対し、私たち吉備高原学園高等学校は、30年以上にわたる実績と「全寮制・全日制」という独自の環境で、具体的な解決策を提示しています。
生活リズムの乱れには、規則正しい寮生活を
不登校の大きな要因である生活リズムの乱れに対し、本校では栄養バランスの取れた食事と、仲間と共に送る規則正しい寮生活で、心と体の健康を取り戻す土台を築きます。
学習への不安には、一人ひとりに合わせた学び直しを
英語や数学については学習の進度や定着度合いにも開きがあるため、個別指導による対応だけでは十分とは言えません。そのため、習熟度別授業を通して分かる喜びや学ぶ意欲を引き出し、一人ひとりに合わせた学びの機会を提供します。
人間関係の悩みには、新しい環境での再構築を
過去の人間関係で傷ついた心も、全国から集まる同じような経験を持つ仲間との共同生活の中で、自然と癒され、新しい信頼関係を築く力が育まれます。
無気力・不安には、夢中になれる専門コースを
マンガ・アニメーション、クラフトデザインなど10の専門コース で「好きなこと」に打ち込む経験は、失いかけた自信と「自分にもできる」という自己肯定感を取り戻す大きなきっかけとなります。
将来への不安には、公私協力の安定した基盤を
本校は岡山県と民間の学校法人が協力して運営する全国初の「公私協力方式」の高校です。公的な信頼性と、グループの大学・専門学校への特別推薦や入学金免除といった具体的な進路支援が、保護者の皆様の将来への不安を和らげます。
環境を変え、新しい一歩を踏み出したいと考えるお子さんにとって、安心して再スタートを切れる場所がここにあります。
吉備高原学園高等学校では、学校説明会や個別学校見学を随時受け付けており、保護者の方のみの相談も歓迎しています。 まずは資料請求やお問い合わせからでも結構ですので、お気軽にご相談ください。