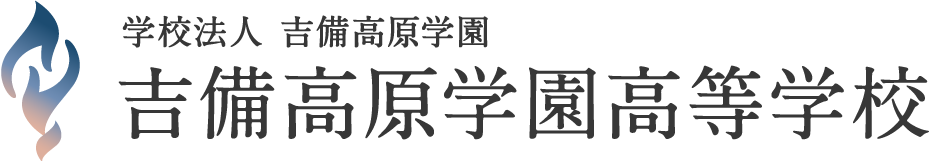- すべて
- 学校の種類と比較
起立性調節障害の中学生と保護者のための高校進学ガイド|全寮制高校の視点から
中学生の中には、体の不調から朝の登校が難しくなり、不登校を余儀なくされる生徒がいます。その原因の一つとしてよく見られるのが「起立性調節障害(OD:Orthostatic Dysregulation)」です。思春期に多い病気でありながら、まだ十分に理解されていない部分もあり、本人や保護者が「怠けている」と誤解されて苦しむことも少なくありません。
本コラムでは、起立性調節障害の中学生とその保護者が 高校進学 を考える際に役立つ情報を、全寮制高校である吉備高原学園高等学校の視点を含めてお伝えいたします。
起立性調節障害とは
思春期に多い自律神経の不調
起立性調節障害は、血圧や脈拍を調整する 自律神経系 の働きが乱れることで、立ち上がったときに血流が脳へ十分に届かず、立ちくらみや倦怠感を引き起こす病気です。小学生高学年から中学生にかけて多く見られ、特に思春期の体の成長とともに一時的に自律神経のバランスが崩れやすいことが背景にあります。
日本小児心身医学会の報告では、中学生のおよそ10人に1人が何らかの形でこの障害を抱えているとされ、不登校の生徒の3〜4割に併存しているというデータもあります。つまり、不登校問題を考える上で欠かせない要因の一つなのです。
「怠け」と誤解されやすい病気
起立性調節障害は、外見からはわかりにくく、特に午前中に症状が強く出ることから「朝起きられない=怠けている」と誤解されることが少なくありません。本人も「行きたいのに行けない」という葛藤を抱え、周囲の理解不足によって自己肯定感を失うことも多く、二次的な不登校やひきこもりへつながる場合があります。
起立性調節障害の原因や症状について
原因
起立性調節障害の原因は単一ではなく、複数の要因が組み合わさって発症すると考えられています。
- 【自律神経の調節異常】
血圧や心拍を一定に保つはずの調節機能がうまく働かず、立ち上がると血液が下半身にたまり、脳への血流が不足します。 - 【循環血液量の不足】
水分摂取不足や体質的な要因により、血液量が少なくなり症状が悪化します。 - 【思春期特有の発育のアンバランス】
身長の急激な伸びなど身体的変化に、自律神経がついていけないことがあります。 - 【心理的ストレス】
学校生活や人間関係、家庭環境などの心理社会的要因が、自律神経の不調をさらに悪化させることもあります。
主な症状
起立性調節障害の症状は多岐にわたります。
- 朝起きられない、午前中に体調が悪化する
- めまい、立ちくらみ、動悸、頭痛
- 倦怠感が強く、授業に集中できない
- 長時間立っていられない
- 気分不良や食欲低下
- 症状の出方に日内変動があり、午後や夕方は元気になることもある
この「午後になると元気になる」特徴が、周囲から「本当は元気なのに学校に行かない」と誤解される大きな原因です。
学校生活への影響
- 遅刻や欠席が増えることで進級や卒業に不安が生じる
- 授業の遅れから学力低下につながる
- 教員や同級生の理解が得られず孤立する
- 自己肯定感の低下、うつ状態の併発
起立性調節障害の対処法
医療的アプローチ
まずは小児科や小児心療内科などでの診断が大切です。治療には以下のような方法が用いられます。
- 水分・塩分の適切な摂取
- 生活リズムを少しずつ整える
- 運動療法(下肢の筋肉を鍛え、血液循環を改善する)
- 薬物療法(重症の場合)
生活面での工夫
- 朝は急に起き上がらず、布団の中でストレッチをしてから立ち上がる
- 水分をこまめに摂取する
- 睡眠不足を避け、就寝・起床リズムを安定させる
- 午前中は無理をせず、調子の良い時間帯に活動する
家庭での支援
- 「怠けではなく病気」であることを家族が正しく理解する
- 学校に行けないときも、責めずに受け止める
- 家庭学習や趣味を通じて自己肯定感を支える
学校との連携
- 遅刻や欠席がやむを得ないことを理解してもらう
- 保健室登校や分割登校など柔軟な対応を相談する
- ICTを活用したオンライン学習や自宅学習を出席扱いにする制度を確認する
起立性調節障害の生徒に最適な高校は?
高校進学に際しては、子どもの体調や生活リズムに合わせて「定時制」「通信制」「全日制」から選択肢を検討する必要があります。
定時制高校
- 【メリット】
午後や夕方から授業が始まる学校もあり、午前中に体調が整わない生徒には通いやすい。 - 【デメリット】
中退率が高い傾向があり、自主性が求められる。進学実績は学校によって差がある。
通信制高校
- 【メリット】
登校日が少なく、自分の体調に合わせて学習できる。オンライン学習やレポート提出中心であるため、高校を卒業するためのハードルが低い。 - 【デメリット】
自己管理が求められる。友人関係が築きにくい場合がある。
全日制高校
- 【メリット】
学校行事や部活動などで充実した学校生活を送れる。 - 【デメリット】
朝の登校が必須のため、遅刻や欠席が多いと進級・卒業が困難になるリスクがある。
全寮制高校(全日制)
- 【メリット】
〇 基本的な生活習慣や食生活が安定することで、起立性調節障害の症状が大幅に改善するケースが多い。
〇 通常の全日制高校ではデメリットになってしまう朝の「登校」の負担がほとんどないため、ストレスの軽減にもつながる。
〇 起立性調節障害の生徒を受け入れている全寮制高校であれば、クラスや寮室に自分の背景や気持ちに共感してくれる仲間がいる。
〇 全寮制高校では、学校生活はもちろん、生活全般のサポートがあるため、保護者の負担が大幅に軽減される。
- 【デメリット】
〇 共同生活に慣れるまでは、心身ともに疲労やストレスが蓄積してしまう。
〇 個室の寮でない場合は、一人になれる時間が少ない。
高校選びのポイント
学校に確認すべきこと
- 遅刻や欠席に対する対応は柔軟か?
- オンライン授業や在宅学習を「出席扱い」にできるか?
- 学校にカウンセラーや相談員は配置されているか?
- 定期試験や課題提出について配慮はあるか?
- 進学・就職のサポート体制は整っているか?
- 学校全体に起立性調節障害への理解があるか?
保護者が整理しておくこと
- 子どもの体調リズム(午前は不調、午後は活動的など)を把握しているか
- 本人が望む高校生活のイメージを聞き取っているか
- 医師の診断書や配慮依頼文を準備しているか
- 学校見学や個別相談で具体的に質問する準備をしているか
子どもと一緒に考えること
- 毎日登校するのが現実的か?
- 将来は大学進学を考えているか?就職か?
- 同級生との交流をどの程度大切にしたいか?
- 自宅学習で自己管理できるタイプか?
保護者向けQ&A形式
Q1. 起立性調節障害は「甘え」ではないのですか?
A. いいえ。自律神経の不調による医学的な病気です。本人の努力不足ではありません。保護者が「怠けているのでは?」と疑うと、子どもの自己肯定感が大きく損なわれます。
Q2. 高校進学では全日制を諦めなければならないのでしょうか?
A. 必ずしもそうではありません。ただし全日制は登校時間が厳格であり、症状が強い生徒には負担が大きいことが多いです。体調や希望を考慮し、通信制や定時制も含めて選択肢を広く検討してください。
Q3. 通信制高校は進学に不利になりませんか?
A. 通信制でも大学進学実績を持つ学校は多くあります。学習サポートや進学指導が充実している学校を選べば問題ありません。むしろ体調に合わせて無理なく学習を続けられる点が大きな利点です。
Q4. 学校にどのように相談すればよいですか?
A. 医師の診断書を持参し、欠席や遅刻が症状によるものであることを説明しましょう。「どのような配慮が可能か」を具体的に相談することが大切です。保健室登校や分割登校を提案できる学校もあります。
Q5. 保護者として一番大切なことは何ですか?
A. 子どもを責めないこと、理解し支えることです。そして「進学=ゴール」ではなく、「健康を守りながら将来につながる学びを続けること」を目標にして、一緒に最適な道を探していく姿勢が何より大切です。
Q6. 寮生活をすることが症状の改善につながりますか?
A. 環境が変わることには大きな意味があります。寮での共同生活を通して心身ともに大きく成長することが、根本的な症状の改善につながります。
最後に
起立性調節障害である中学生にとって、高校選びは「どんな学校に行けるか」よりも「どんな環境なら自分らしく過ごせるか」が鍵となります。また、高校生活を通して「どんな自分になりたいか」というポジティブなビジョンを持てるかどうかも重要です。そのためにも、より多くの情報を集め、本人、保護者、学校の先生や相談員の方々などが連携し、様々な視点からじっくりと相談することが大切です。
吉備高原学園高等学校をはじめ、全国には、起立性調節障害の生徒を受け入れている全寮制の学校があります。朝起きられないので、定時制や通信制しか選択肢がないと決めつけるのではなく、全寮制というスタイルを通して起立性調節障害と向き合い、高校生活3年間で心身ともに成長することを目指してみませんか?