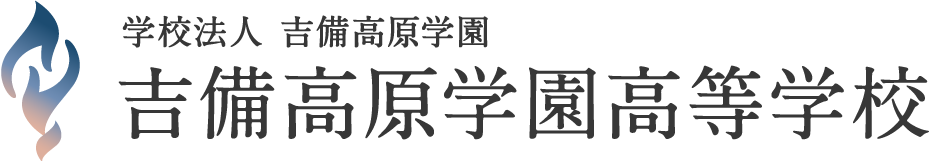- すべて
- 学校の種類と比較
不登校でも行ける全日制高校|不登校経験を乗り越えて全日制高校を目指す中学生・ご家族へのガイド
「不登校でも行ける全日制高校」を探している方にとって有益な情報をお届けし、様々な可能性や選択肢の中から自信をもって進路選択をしていただきたいと考え、このコラムをお届けします。
近年、小学校や中学校で「不登校」とされる児童生徒は増加傾向にあり、社会的にも大きな問題となっています。しかし、現状では不登校になる児童生徒を生み出さないための抜本的な教育改革が成果を結んでいるとは言い難い状況です。国の制作としては、文部科学省の「COCOLOプラン」を中心とした取り組みや「学びの多様化学校」の設置などがありますが、どちらかと言えば、不登校になった児童生徒に対するサポートの拡充や多様な学び方を提供するというものが中心となっています。
また、各都道府県においても、「不登校対策」の中心的な取組みの一つとして、全日制の公立高校の入試改革や多様な生徒を受入れるための学校改革があります。そのため、中学校で欠席が多かった生徒の進路についても多様な選択肢から選べるようになっています。
文部科学省の支援方針と制度について
COCOLOプラン:誰一人取り残さない学びの保障
文部科学省は2023年3月、「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策(COCOLOプラン)」を発表しています。
その柱は以下の3点です:
1. 全ての児童生徒が学びたいときに学べる場の確保
2. 「心の小さなSOS」を見逃さず、「チーム学校」で支援
3. 学校の風土の“見える化”により、みんなが安心できる学びの場づくり
この計画に基づき「学びの多様化学校(旧・不登校特例校)」の設置促進、校内教育支援センター・スクールカウンセラーなどの配置、ICT活用による早期発見体制の推進が進められています。
学びの多様化学校(不登校特例校)
文部科学省が指定する「学びの多様化学校」は、不登校経験者向けに特別な教育課程を編成する学校です。
その特徴は:
・教育課程の柔軟化(授業時間が短く、体験型学習や習熟度別編成を導入)
・少人数や個別指導の活用
・教育支援センターやフリースクールなど外部機関との連携による支援体制
2025年時点では35校が指定されており、今後は全国300校規模で分教室型を含む拡充を目指しています。
都道府県ごとの全日制公立高校の取り組みや制度
東京都:チャレンジスクール・エンカレッジスクール
東京都では、不登校経験者が安心して学べる全日制高校として、チャレンジスクールやエンカレッジスクールを設置。少人数授業、面接や作文による選抜、生活支援・カウンセリングが充実しています。
神奈川県:クリエイティブスクール制度
神奈川県立高校に設けられたクリエイティブスクールでは、学力や内申書より意欲や個別理解を重視。少人数制・複数担任・朝学習・キャリア教育など、「普通科の形を取りながら柔軟な支援がある学校」として評価されています。
埼玉県:不登校特別選抜制度
埼玉県には、不登校経験者向けの特別入試枠「不登校特別選抜」があり、作文・面接・推薦などで選考。入学後は個別学習計画や定期カウンセリングが提供されます。
その他地域の例
他の地域でも、総合学科・単位制高校、独自の柔軟な選抜枠や支援制度を設ける高校が増えています。地域によって制度には差があるため、自治体ごとの情報確認が必要です。
全日制の私立高校の取り組み事例
柔軟な姿勢を持つ私立高校
私立高校の中には、不登校経験者に対して柔軟な姿勢で入学対応をする学校もあります。選抜基準は学校ごとに異なるため、説明会や個別相談で「学ぶ意欲」や「現在の状況」を丁寧に伝えることが重要です。
不登校生を受け入れている全寮制高校という選択
欠席が多い生徒の受入れを表明している高校は増えていますが、入試制度の中で配慮するからと言って、入学後も手厚いサポートをしてくれるとは限りません。
また、不登校の経験が無い生徒が大半を占める学校に入学した場合、過去の経験や気持ちを共有できる仲間と出会うことも難しいかも知れません。さらに、日々の生活習慣の確立や公共交通機関を利用しての長時間の通学なども大きな課題となってきます。
しかし、吉備高原学園高等学校のように、不登校経験者を積極的に受け入れている全寮制の高校であれば、共感できる仲間との出会いや、寮生活を通じた生活習慣の改善などが無理なく実現できます。そのため、全日制+全寮制というスタイルは「自分を変えたい」と思っている皆さんにとっては最適な選択と言えます。
全日制高校を選ぶべき理由
通常の学校生活を再体験できる
友人との日常、行事、部活動など、中学生時代にできなかった“学校らしい時間”を取り戻せるのが全日制の魅力です。
自尊心と社会性の回復
仲間との共同作業や役割を通して「自分にもできる」という実感が、自己肯定感や対人関係能力の回復につながります。
将来の進路選択肢が広がる
大学進学や専門学校、就職といった進路に対応する制度が整っており、進路資料や求人も全日制ベースで提供される傾向があります。
多様な支援制度が整いつつある
文科省のCOCOLOプランに基づく支援、各自治体の制度、公立・私立の実践…さまざまな選択肢があり、本人の希望に応じた環境を選びやすくなっています。
通信制高校と比較したメリット・デメリット
全日制高校のメリット
•日常的な友人との関わりと共同生活が得られる
•行事や部活動を通じて学校の一員としての経験ができる
•学校が生活リズムや進度を管理してくれる安心感がある
全日制高校のデメリット
•毎日通う負担が大きく、過去の不登校が再燃するリスクもある
•欠席が多いと進級・卒業に悪影響が出る可能性がある
通信制高校のメリット
•自分のペースで学習でき、登校負担が少ない
•留年リスクが低く、進路対応が柔軟
•不登校・中退経験者への配慮が多く実績も多い
通信制高校のデメリット
•同年代との関わりや学校行事など、学校ならではの体験が得づらい
•自律性が求められ、自己管理力が弱いと学習が滞る可能性がある
転入学や高校での不登校対策のポイント
制度や支援内容を正確に把握
各都道府県の制度(例:東京都のチャレンジスクール制度、神奈川のクリエイティブスクール、学びの多様化学校など)について、自治体や学校窓口で詳細を確認しましょう。
説明会・個別相談への積極参加
学校の雰囲気や支援方針を感じとるにはまず現地へ。相談時には「不登校経験があること」「まだ通えるか不安であること」を正直に伝え、支援体制を確認しましょう。
学習・生活リズムの準備
転入先で必要な単位や出席日数、学習内容に対応するために、家庭で生活リズムの再構築や自宅学習の習慣づくりを少しずつ進めましょう。
メンタルサポート体制の確認
スクールカウンセラーやSSW、校内・外部の支援機関の体制を事前に把握しておくことで安心度が高まります。
家族・専門機関との連携
不登校の再出発には家庭の支えが不可欠です。専門機関やNPOと連携しながらサポート体制を整えることで、本人も家族も安心して歩みを進められます。
まとめ
不登校は「終わり」ではなく、再スタートのプロセスです。「学校に戻りたい」「友だちと普通に学びたい」という素直な気持ちは、何より尊重されるべきです。文部科学省のCOCOLOプランや「学びの多様化学校」、各自治体や学校の支援制度を活用しながら、本人とご家族が安心できる進路をじっくり探していきましょう。